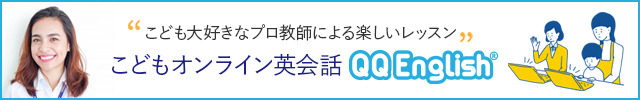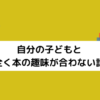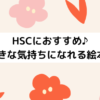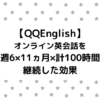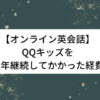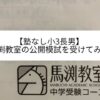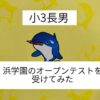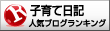子どもの英語は何歳から始めるのがベスト?
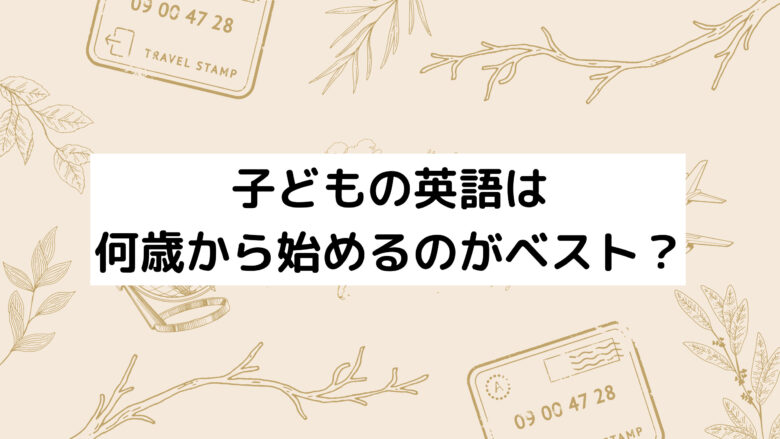
現在オンライン英会話QQキッズを週6で受講中の長男は、小学校1年生の3学期から英語学習を開始しました。
本人の「英語をやりたい」というタイミングを待ちつつも、私の中では小学校に上がってからという想いがありました。
正解があるテーマではありませんが、いつから取り組むべきか気になるかたも多いのではないでしょうか?
今回は子どもが英語学習を始める時期について考えてみたいと思います。
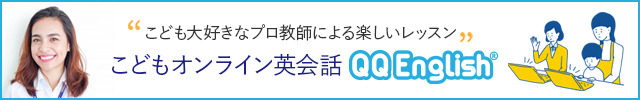
まずは日本語の習得を優先したい
私が小学生になってから英語を始めるべきだと考える理由はただ1つ。
日本で暮らす以上、まずは母国語からでしょ!
個人的に小学校に入学するまでの6年間は、美しい言葉で綴られた絵本を浴びるように読み聞かせたい!との想いがとても強かったんです。
オンライン英会話を始めると決めてからは英語絵本も取り入れていましたが、その読書量の差は圧倒的でした。
私の中で幼児期における母国語の習得とは、短い文章なら自分ですらすら読めるというもの。
絵本でいうと「せんろはつづく」と「つみきでとんとん」が目標でした。
(我が子はこの2冊が特にお気に入りだったため。)
ただ、いきなり絵本を手渡すのも難しいかと思ったので、前段階として使用していたのがこちら。
将来役立つことわざや名言で構成されているテキストで、幼稚園に登園する前に声に出して1ページずつ読んでいました。
「あめんぼあかいな あいうえお」などの演劇部発声練習のような文から、「ふるいけや かわずとびこむ みずのおと」のような知っておきたい和歌までバラエティに富んでいて飽きがこなかったところが良かったです。
あとは先取り学習で取り組んだ参考書の問題は全て音読していました。これは小2になった今でもやっています。
元々幼稚園の間は英語には力を入れないと決めていましたが、子供の様子を見ていても小学校入学のタイミングでやっぱりちょうど良かったなあと思います。
幼児期から英語を始めるべき子ども
私はまず外国語より母国語!という考えの持ち主ですが、たとえ幼児期でも始めるべき!と思うタイプが2選あります。
ひとつずつ見ていきましょう。
・両親の海外赴任などで一時的でも海外に住む子ども
いわゆる駐在っ子ですね。適応せざるを得ないパターンです。
仮に3歳などで海外に行くとしたら、その時点でまだ子供は日本語の習得は不完全にあると思うのですが、この場合は優先すべきは英語です。
“住む"以上は習得するしかないので、年齢関係なく英語学習を開始すべきかなと考えています。
・DWEなどで親が腹をくくって教育するパターン
実は私、DWE(ディズニー英語システム)ユーザーを世の中の教育ママパパで一番尊敬してるんです。
日本にいながらにして、自力で外国語を習得させてやろうというその決意。
いかに教材や子供の機嫌と毎日向き合うかが重要になってくると思うんですが、もし自分なら・・挫折の未来しか見えない。
たまにSNSなんかで発音完璧なDWEキッズが絵本を読んだりしてるのを見ると、その裏にある大人の努力を感じ涙が出そうになります。
どんな先取りも相当な覚悟とともに成り立っているんですけどね。ゼロから語学はやっぱりすごいなーって思ってしまう!
早期教育ブームに惑わされない
小学校3年生からの英語教育が必修化した今、つまづきや抵抗感をなくすためにも授業開始前に家庭での先取りは必須と言えるでしょう。
英語に加えて現代の子どもってプログラミングやダンスまで必修化していて、毎日をこなすだけでも大変です。我が子を思えば少しでも早く英語を始めたい!という気持ちはすごくわかります。
ただ実際に小学生の子供を持つ親として強く思うのは、日本で教育を受ける以上「国語力」から目を背けることはできないということ。逆に言えば、私は国語力なくして英語は身につかないとすら思っています。
小学校に入学したからといって自然と身につくわけではありません。まさにそれまでの積み重ねが大切なのです。
英語に関して言えば我が家の長男をみていただければわかる通り(9ヵ月で英検5級レベルは完璧)、小学校に上がってからでもちゃんと親子で向き合えば十分習得可能です。
子どもの英語開始時期を検索して山のようにでてくる「早期教育」というワードに惑わされる必要は全くありません。どうかタイミングや順番を間違わずに、お子さんを導いていただけたらと思います。
まとめ
私の中で英語を始めるということに対する結論は・・・
乳幼児期からやるなら覚悟を持ってやるべし!でも国語力がある程度身についた小学校入学後からでも十分習得可能!
週に1回グループレッスンに放り込んで先生に丸投げし、家ではノータッチ!何をしてるかわからない!となるくらいならやらないほうがマシです。
自分が子供の頃とは状況は全く違います。私自身、これからも見極める力を持って慎重に取り組んでいけたらと思います。